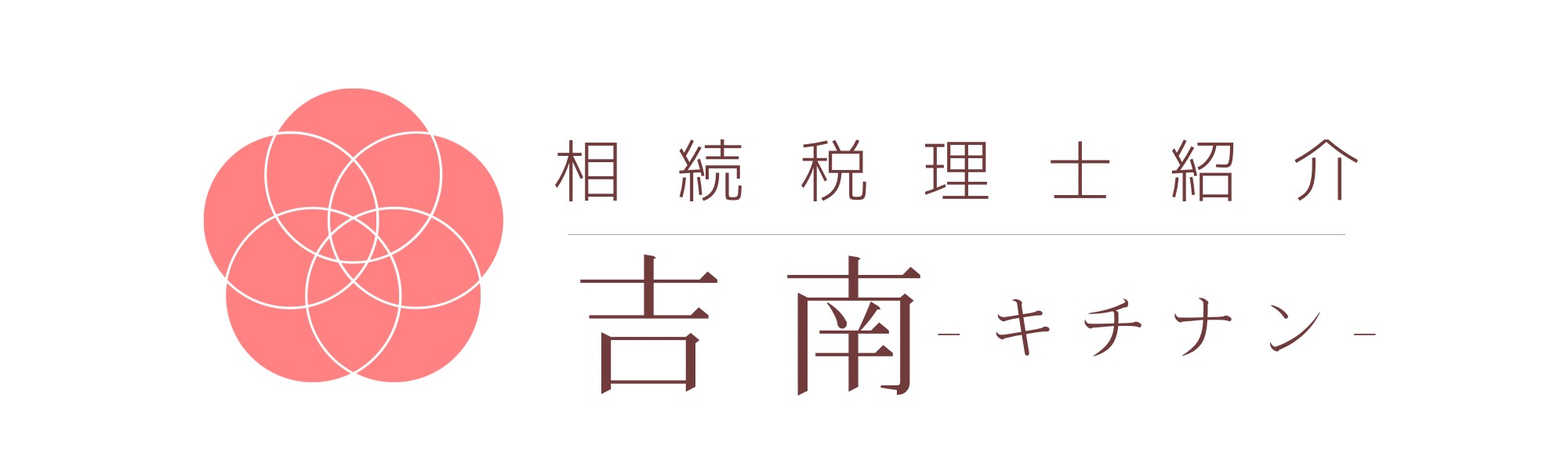実家の名義変更|生前贈与と相続で税金は違う?手続きの流れを解説!

同居の妻や子供など、特定の相手に自宅を譲りたいと考えるケースは少なくないでしょう。
遺言書などで相続財産を指定することもできますが、生前贈与で先に名義を書き換える方法も効果的です。
しかし生前贈与には、相続が発生した場合に見込まれる相続税よりも税額が高くなったり、将来的に相続人の間でトラブルを招く危険があります。
そこでこの記事では、実家を贈与して名義を変更する場合の手続きの流れや注意点を詳しく解説していきます。
生前贈与で実家の名義変更は可能なの?
同居している長男に自宅を譲りたいのですが、生前贈与で自宅の名義は変更できますか?

名義変更自体は可能です。しかし、相続よりも税金が高くなるなどの恐れがありますから、慎重に検討すべきでしょう。

実家の生前贈与には贈与税がかかる

お金に限らず、財産を贈与した場合には受け取った人に贈与税がかかります。将来的に相続するはずの実家の場合でも同様です。
親から子への贈与は「特例贈与財産」と呼ばれ低い税率が適用されますが、住宅のような高額の財産を贈った場合には贈与税も高額になりかねません。
贈与税のシミュレーションは必須
贈与税は相続税に比べて税率が高く基礎控除額も小さいため、納めるべき税金は高くなりがちです。
生前贈与を検討する際には、できるだけ正確なシミュレーションが必須といえるでしょう。

相続税よりも贈与税の方が税率や控除額の面で不利になりがちであることに加え、相続時であれば利用できる減税の特例が贈与の場合は適用されないなどのデメリットも生じます。
相続税と贈与税を比較して、大きな不利益を生まない方法を考えることが不可欠です。
相続時精算課税制度は慎重に検討
暦年課税での贈与税の非課税枠は110万円と、住宅を贈与するには心もとない金額ではありますが、「相続時精算課税制度」を利用すれば2,500万円の贈与までを非課税とすることができます。
しかし、この制度を選択すると暦年課税に戻すことができず、その後に少額な贈与があった場合でも確定申告の義務が生じます。
実家を生前贈与するメリットは?

税金についてはデメリットが生じるリスクもあるんですね。では生前贈与のメリットはなんでしょう?

ご本人が、確実に希望の相手に財産を譲ることができます。その他のメリットも見ていきましょう。

相続登記の負担軽減
不動産の所有権を取得した場合、登記簿に記載された所有者を変更しなければなりません。
しかし、相続登記は複数の利害関係者の調整などを要し、書類を集めるだけでも困難なケースも少なくありません。
生前贈与によって所有権を移転しておけば、それらの負担から解放されることとなります。
公正証書遺言があれば相続時のトラブル回避になる
特定の相手に資産を譲る場合には、生前贈与のほかに遺言を残すという方法も存在します。
生前贈与を選択する場合は、相続時のトラブル回避のために公正証書遺言を作成しておくとよいでしょう。
生前贈与をしておけば住まいを確実に譲ることはできますが、相続が発生した時には「生前贈与を受けた人は、被相続人の生前に特別な利益を受けた」ということからトラブルを招くリスクも否めません。
トラブル回避のためには、生前贈与とともに遺言書の作成を検討することが望ましいでしょう。
実家を生前贈与するデメリットは?
生前贈与と相続を比較して、税率以外のデメリットはありますか?

土地・建物の評価方法が相続と贈与では異なるため、資産価値が高く計上されがちなこともデメリットです。

資産価値が下がると損をする場合がある

相続の場合には土地・建物の評価は市場価格の7割程度に抑えられる仕組みですが、贈与の場合には単純に市場価格で評価します。
このため資産価値が高く計上され、税額が高くなりがちなこともデメリットです。
不動産の価格は景気の影響などを受けるため必ずしも贈与時点の方が高額であるとはいえませんが、建物に関していえば経年によって資産価値が減少するため、築年数が若いタイミングで贈与すると評価額が高くなります。
また、相続だけに適用される減税制度が贈与では利用できないことを覚えておきましょう。
特別受益の持ち戻しにより相続分が減る可能性がある
生前に特定の相手に贈与をすることは、相続財産が減少することを意味しています。
このため自宅の贈与を受けた相手は「被相続人の生前に特別な利益を受けた」と考えられ、相続時に受け取る財産が減らされる可能性が生じるのです。これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。
相続では、遺族のために一定の遺産を保全するための制度として「遺留分」がありますが、生前贈与によって他の相続人を遺留分を侵害している場合には、贈与を受けた人が他の相続人の損害を補填しなければならなくなる可能性が生じるのです。
実家の生前贈与と相続はどちらが得なの?

現実的には、実家の生前贈与と相続ではどちらが得なのでしょうか?

相続財産の額や資産の内訳などに応じて異なるため一概には言えませんが、ある一定のケースでは、生前贈与が有利になる可能性があります。

資産状況などにより単純な比較は難しい
それを利用してもさらに相続税が発生する場合には「配偶者への居住用不動産贈与の特例」を利用して生前贈与をすることが節税につながる可能性もあるでしょう。
税率は相続税のほうが低い
前述したとおり、税率は贈与税よりも相続税の方が低く設定されています。
仮に課税対象額が1,000万円だった場合、相続税の税率は10%であるのに対し、贈与税は30%(控除額90万円)です。
税額を計算すると、相続税は100万円、贈与税は210万円となります。
しかし現実的には、財産の算出方法や控除額などに大きな違いがあるため、この算出方法も正しいとはいえません。
相続では資産から負債を除いた正味の財産で計算するのに対し、贈与ではあくまでも贈与財産が基礎となります。
また、相続の基礎控除額は3,000万円プラス600万円×法定相続人の数とされており、相続財産がこれ以下であれば課税されません。
名義変更の税金は生前贈与のほうが高い
不動産の所有権を移転する場合、相続税や贈与税以外にも税金が発生することも押さえておきましょう。
生前贈与で実家の名義変更をする流れ
実際に生前贈与で自宅の名義を変更するとしたら、どのような手続きが必要でしょうか?

それでは、贈与から登記、納税までの流れをざっと説明します。


相続人を確認し受贈者を決める
第一にすべきことは相続が発生した場合に相続人となる可能性がある人をすべて確認した上で、贈与する相手を決めることです。
この段階で「想定される相続人」を抽出しておくことが、後々のトラブルを防止する上で大切なことといえるでしょう。
相続人が分かれば法定相続分などを試算することも可能で、他の相続人の遺留分なども考慮することができます。
実家の相続税評価額を算出する
贈与する相手が決まったら、相続時に想定される評価額を試算しましょう。
相続税の評価額は、土地は相続税路線価もしくは倍率方式で算出することとされ、建物は固定資産税評価額がそのまま適用されます。
相続税路線価は国税庁のHPで公表されており、建物の評価額や倍率方式の土地の評価のもととなる固定資産税評価額は市町村で取得することができます。
贈与税の計算

贈与での不動産の評価額は時価、つまり一般的な市場での取引価額が適用されます。
取引価格を知るためには不動産会社に依頼するか、一括査定サイトなどのサービスを利用するのが便利です。
この価格をもとに適用される控除額や税率を用いて贈与税を計算しましょう。
親から子への贈与よりも夫婦間の贈与の方が適用される税率が高くなることにも注意が必要です。

必要書類を準備する
贈与という行為自体は両者の意思が合致すれば成立しますが、それを第三者に明確に示すためには書面を作成することが不可欠です。
また贈与する財産が不動産の場合は、所有権移転登記も必要になります。
これらの手続きには、登記識別情報通知(もしくは権利証)や贈与者の印鑑証明書、受贈者の住民票などの準備が必要です。
贈与契約書を作成する
登記簿上の所有者を変更するには、その原因となる「贈与」を第三者に示す書類が必要ですから、贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書には特定の様式があるわけではありませんが、贈与の対象物となる不動産を明確にするため、登記事項証明書をもとに正確に記すことが不可欠です。
所有権移転登記を行う
贈与を登記原因とした所有権移転登記を完了することで、第三者に対しても「名義を変更した」という事実を明らかにすることができます。
所有権移転登記は本人でも申請することができますが、申請書類の作成には専門的な知識を要するため、司法書士に依頼するのが確実でしょう。
贈与税の申告・納税を行う
登記申請が完了すれば、贈与という行為自体に必要な手続きは完了です。
これをもとに、翌年の2月1日〜3月15日の期間内に、贈与税の確定申告をするのが最後の仕事です。
特に減税の特例などを利用する場合には、専門的な知識を要します。期間内に申告ができなければ減税が受けられなくなる恐れもあるため、税理士に相談するのが望ましいでしょう。
実家の生前贈与でかかる税金・費用
かなり多くの手続きがあるようですが、税金や費用はいくらぐらいになりますか?

税金は評価額によって大きく異なります。その他の費用も含めて見ていきましょう。

贈与税
住宅を生前贈与することで最も大きな負担となる可能性があるのが贈与税です。
暦年課税による贈与税の計算では、土地・建物の市場価格から基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象となります。

贈与額が大きければ税率も上がる仕組みのため、税額が大きくなるケースでは相続時精算課税なども検討するのが良いでしょう。
不動産取得税
税率は土地・建物ともに本則では評価額の4%ですが、住宅用の不動産であれば3%とする軽減措置が取られており、さらに土地については評価額が半額で計算されます。

登録免許税
登録免許税は、所有権移転登記にかかる税金です。
贈与を登記原因とする登録免許税は、土地・建物ともに固定資産税評価額の2%とされています。
印紙税
印紙税は、契約書などの課税文書に貼付して納める税金です。
売買契約書では不動産価格に応じて税額が定められていますが、贈与の場合は無償であるため一律200円です。
司法書士報酬
登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士に対する報酬が必要です。
報酬の額は規定されていないため依頼する司法書士によって異なり、登記対象の不動産の権利関係などによっても差異が生じます。
建物1棟、土地1筆の所有権移転であれば、おおむね4〜5万円程度が一つの目安でしょう。
実家の生前贈与に関するよくある質問
大まかな流れや注意すべきポイントを説明してきましたが、ここで実家の生前贈与に関するよくある質問を確認しておきましょう。

名義変更、つまり「所有権」という権利の登記に関しては、期限が定められているわけではありません。
しかし、「登記が無ければ第三者に対抗できない」とされる通り、登記をしなければ正当な権利を持つ者として法律上の保護を受けることができないのです。
万が一他人が所有者として登記したとしたら、所有権を主張できなくなるかもしれません。
赤の他人が所有権を登記するというのは考えにくいケースであるともいえますが、登記を変更していない場合にはそれ以外にもさまざまな支障が生じます。
不動産の所有者は登記で判断するのが基本ですから、所有者を変更していなければ売買や賃貸などの法律行為ができません。
また名義を変更せずにさらなる相続が発生した場合などでは、権利関係が複雑化して登記が困難になる恐れも生じます。
事情に合わせて適切な方法を検討しよう

さまざまな事情で生前贈与を検討する機会があるかもしれませんが、贈与が有利か、相続が有利かはケースバイケースで、一概に決めることはできません。
贈与を検討するに至った動機や家族に遺す資産の額や内容など、それぞれの事情に合わせて検討することが大切です。
専門的な知識を要する分野であるため、税理士や司法書士など専門家の力を借りて最善の策を考えましょう。